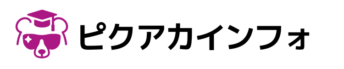著者が著書を紹介するという「ツクレル」さんの企画、面白いと思い参加させていただきました。「ツクレル」さんに来られているということは電子工作への感度高めな方な読者の方が多いかと思いますので、この本を読むことでどういったことが学べるのかを紹介させていただきます!

プログラミング教室での経験をもとにした「電子工作」を学べる一冊!
私が代表を務めるニャンパス株式会社は、ウェブサービスやスマートフォンアプリ開発のかたわら、越谷レイクタウンにてコワーキングスペース「HaLake(ハレイク)」を運営しています。そのコワーキングスペースにて、現在でも私がプログラミングを小中学生に対して教えています。
その時々によってテーマを変えているのですがたとえば「マインクラフト」のModを使ったプログラミング体験や、「Unity」を使ったゲーム開発など、子どもたちにプログラミングの楽しさ伝えられるような様々な題材を選んでいます。その中の一つとして「電子工作」のレッスンがあります。
そんなプログラミング教室で扱ってきた「電子工作」のレッスンの経験を生かし、電子工作を基本から「Arduino」を題材にして少しずつステップアップしながらプログラミングを学んでもらおうという趣旨で書いた本が『ゼロからよくわかる! Arduinoで電子工作入門ガイド』です。
ちょうど今から2年前に出させていただいたのですが、改めてAmazonのレビューでを見てみると大変好評を頂いていて嬉しい限りです。
プログラムを書いて「光る」「動く」体験を!
「電子工作」の本といっても「Arduino」を題材にしていて、パソコンからプログラムを送り込む事で、LEDを光らせたり、モータを動かしたりといった実際に手を動かして体験できるようになっています。こういった経験は年代を超えて楽しい経験だと思っていて、周りに詳しい大人がいない子ども、親子で一緒に学びたいと思う方々、あるいは学校でそんなこと習わなかったけど興味が出てきたというような社会人、ご年配の方々などぜひ体験してもらいたいと思っています。
せっかく「電子工作」をテーマにしているのですから、自分の書いたプログラムが思い通りに現実の世界に影響を与えている(といってもささやかではあるかもしれませんが)というのはやってみないと分からないワクワクする体験です。
電子工作の基本から初めて最終的にはバギーの完成!
この本はざっくり「基本編」と「実践編」に分かれており、「基本編」では電子工作とは?Arduinoとは?といった基本から始まり、どこでArduinoを入手できるのか、どんな事ができるのか、Arduinoの動かし方やシンプルなプログラムの書き方というステップをイラスト入りで説明しています。徐々に扱う電子部品を増やして、少しずつできることの範囲を広げるように解説をしていています。
「実践編」では「基本編」で説明してきたことをベースに以下のような具体的で、面白い(実際にプログラミング教室で反応が良かったもの)を中心に丁寧に作り方を解説しています。1章から4章までが「基本編」、5章から8章までが「実践編」となっています。今回は「実践編」で作っているものを紹介します。
作例紹介: 5章 近づくと光るイルミネーションを作ろう
Arduinoを用いて、様々な色で光る「フルカラーLED」を同時に何個もつなげて、イルミネーションとして光らせます。さらに、人感センサーと組み合わせることで、人が近づくと自動で点灯させる方法を説明しています。


作例紹介: 6章 リモコンで動かせる扇風機を作ろう
Arduinoを使って小型の扇風機を作ります。扇風機にはモーターと赤外線を使い、リモコンでモーターを回転させることで扇風機にしています。夏場にはもってこいのテーマです。


作例紹介: 7章 インターネットと連携しよう
話題の「IoT」を意識したテーマになっていて、図のようにスイッチを押すと、Twitterに投稿を行うという仕組みを解説しています。インターネットのサービスを利用するので、6章までと毛色は違ってきますが、物理的な操作(この場合ではスイッチを押すこと)が、インターネットの世界に伝わるという面白い体験が出来ます。

作例紹介: 8章 ロボット風バギーを作ろう
最後の章はここまでの集大成になりますので、順を追って説明はしていますが割と難易度は高めになっっていて、ロボット風のバギーを作ろうというテーマです。モーターで前進でき、LCDモジュールに表情を表示させ、合成音声を使って喋らせるという、まさにロボット的なバギーの作り方を解説しています。また、この章でははんだ付けにも挑戦してもらえればと思い、LCDモジュールの取り付けのところで解説しています。

ゼロからArduinoを始めよう!
だれだって最初は「電子工作」の「で」の時も分からない初心者だった時があるのですから、この本が「電子工作」に興味を持ってもらえるきっかけになってもらえると著者として幸せです!
(登尾徳誠)
]]>