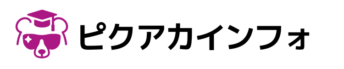Single Board Computer(シングルボードコンピューター)とは何か
Single Board Computer(以下SBC)とはマザーボードにCPUやRAM、電源基盤が最初から搭載されており、主にLinuxが走るような小型のコンピューターボードのことを指す。代表的な物ではラズベリーパイ財団から発売されているRaspberry PiやIntel社から販売されているIntel Edisonなどがある。近年ではRaspi ZERO WやOrange Pi、Nano Pi、C.H.I.Pなど様々なSBCが登場しASUSのような大手PCメーカーもSBC分野でTinker Boardを市場投入し始めている。
国内においてもCHIRIMEN BoardというオープンソースSBCプロジェクトで、大手通信キャリアや大手ブラウザベンダーまでもがこの市場に参入をし始めている。いずれの共通点もIoTを背景として、WEBの世界観を物理層に持ち込むことを目的としている場合が多い。
Single Board Computerの市場動向について
SBCで代表的なRaspberry Piは2012年の発売以来、世界で約1300万台が販売されている。当初は小型の「教育用コンピューター」として販売されたが2014年頃からはIoT市場への期待が高まったことに応じて、小型化と計算能力の高度化、省電力化が推進され、価格単価も下がっている。 2008年にSBCの最初期として登場したBeagle Boneは発売当時$128であったが、Raspberry Piの登場以降Geekな開発者を中心に熱が高まり、続々と安価でより小型化されたSBCが市場に投入されている。現在ではわずか$6ほどでWiFiやBLEなどのラジオモジュールが搭載され、1.2GHz 512MbのRAMを搭載したSDカードサイズのSBCなども市販されるようになっている。
このようなムーブメントは「コンピューターのクラス形成に関するベルの法則」や「ムーアの法則」の代表的事例の一つだと言えよう。SBC群が急激に安価かつ高度化している現象の背景にあるのは市場の需要の高まりだけではない。それにはスマートフォン市場も関係している。年間約15億台出荷されているスマートフォン市場において約9割のシェアを誇る
(英)ARM社のCPUを採用することによる回路基盤やソフトウェアの共通化である。現存するSBCのほとんどは、ARM社の設計したCPUを搭載することで、部品と基盤の共通化を行い、すでにインターネット上で構築されてきたオープンソース資産を再利用し、より充実した性能とユーザビリティを市場に提供できるようになっている。
IoTにおけるSingle Board Computerの可能性
日本国内に目を移すとRaspberry Piなどのコンシューマー向けSBCは、組み込み用途には耐えられず、一般製品に採用できないという説もある。しかし、海外の先行事例を見ていくと軍事用品にコンシューマー向けSBCが採用されている事例や、車載器の中の音声ダッシュボード装置として自動車にも組み込まれ、クラウド経由で道路情報を通知するために用いられる事例もある。特に米国、東南アジア圏において、最終製品へのSBCの組み込み事例は枚挙に暇が無い。信頼性を立証する代表的な事例はISS(国際宇宙ステーション)内での
実験観測用途としてRaspberry Piが用いられているケースだ。宇宙空間では地表に比較して10倍以上の放射線を被曝することになるが、そういった環境でさえ継続的に動作ができることが確認されている。
このようなコンシューマ向けSBCがIoTにおける部品市場に新規参入している背景は、これまでWEBシステムを構築してきたエンジニアがLinuxなどの共通のシステムを用いることでより学習レスでシステム開発ができ、Light weight Languageを用いることでより効率的な開発とデバッグが可能だからである。
実際に先例の車載ダッシュボード機器はnode.jsで実装されている。 日本においては未だ、技術適合等が障壁となり、コンシューマー向けSBCとオープンシステムを製品開発に用いるのはそれほど一般的とは言えない。しかし今後IoTの開発者が増えれば、いずれ海外と同じくコンシューマー向けSBCとオープンシステムを組み合わせた開発手法がより一般的になってくるであろう。ハードウェアの開発コストの約6割以上がソフトウェア開発費に割かれる近年において、このような開発手法に乗り遅れれば、日本の家電メーカーや部品メーカーはさらに海外企業に対して遅れをとることになるであろう。
オープンシステムとIoT
上項3ではコンシューマー向けSBCを直接量産品に用いた具体例を示したが、当然ながら全てのデバイス開発で上記のようなコンシューマー向けSBCを直接的に量産品に乗せられるとは限らない。しかしそういった場合でさえもSBCを開発に用いることには大きなメリットがある。なぜならIntelやASUSなど大手メーカーが販売しているSBC以外のほとんどは“オープンハードウェア”として提供されているからである。
こういったオープンハードウェアを用いた開発は、たとえそのハードウェアが量産品に直接的に採用できなくても大きな恩恵をもたらす。オープンハードウェアはボードや部品の仕様をネット上で公開しているため、量産試作をする場合であっても公開された仕様書と設計書に基づいて基板開発を進められるからである。これにより作業量が大きく減るだけでなく、第三者意見を反映させることで、より開発を効率化できる。さらにオープンシステムを使うことは、セキュリティや信頼性の面でもアドバンテージを得られる。Linuxを発明したLinus Torvaldsの言葉を借りれば「目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない。」ということだ。
オープンシステムやオープンハードウェアはネット上に存在する数多くの専門家からの評価、提案を受け、それらを取り込んで日々進化し続けている。そのため、大抵のバグや脆弱性は発生するたびに取り除かれていく。実際に
Teslaのような先進的な会社はオープンシステムとクローズドなシステムを併せて採用することで、自動車のようなミッションクリティカルな製品の開発を効率化している。こういった動きは日本でも着々と進んでおり、最近発売された
Nintendo SwitchもFree BSDを採用している。つまり、たとえ最終量産品に市販のSBCが乗せられないとしても、プロトタイプでオープンハードウェアのSBCとLinuxのようなオープンシステムを利用することは、その後に待ち構えるプロジェクトにおける壁を越えるブースターとして確実に機能する。]]>