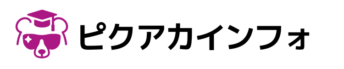そうしたCPUの発熱を拡散するのに用いられるのがヒートシンクになります。ほかにも空冷式(ファン)や水冷式などもありますが、ヒートシンクがもっとも手軽に導入できる熱対策になるでしょう。しかし、ヒートシンクがどれだけ効果があるのか測定してみないことには分かりません。
ということで、この記事では実際にヒートシンクの有無によって、どれくらい温度変化が見込めるのか確認してみました。
条件
今回は簡易的に、Raspberry Pi(以下ラズパイ)のGUIにてYouTube動画を再生しました。動画は720pのものとしています。

今回利用したヒートシンクはヒートシンク 40x30x6 熱伝テープ付 for Pi になります。これはツクレルSTOREで販売しているスターターキットなどで提供しているものです。

付け方はまず電熱テープをCPUに貼ります。

そしてヒートシンクをCPU全体を覆うように(ディスプレイコネクタの間にちょうど収まります)ヒートシンクを付けます。

結論
先に結論からいうと、次のような傾向が見られました。
- ヒートシンクの有無によって、発熱時には10度前後の差が見られました
- 一旦熱くなった後のクールダウンについては大きな差は見られませんでした
動画再生時
まずグラフから紹介します。青がヒートシンクなし、赤がヒートシンクありです。ヒートシンクありのはじまりが低い温度なのは、装着したヒートシンクが冷たかったためと思われます。本来であれば、初期温度はここまでの違いはなさそうです。

しかし、動画を再生し続けてもヒートシンクがあると温度が急上昇しません。ヒートシンクがない場合、最高値が78度に達したのに対して、ヒートシンクがある場合は66度程度でした。約10度前後の差がある状態が続きました。
クールダウン時
動画再生を止めて、CPU稼働率が低くなった状態のグラフが次になります。

ここで特徴的なのは、ヒートシンクがない場合は温度の落下が激しく(元々高熱だったので当たり前ですが)、ヒートシンクがある場合と比べて大差ない温度まで落ちています。最終的な温度として、ヒートシンクの有無で1〜2度の差となっています。
まとめ
今回の内容から分かることとしては、熱暴走を防ぐのにヒートシンクはとても有効だということです。暴走を招かないような温度で利用している限りはヒートシンクはそれほど有効ではありませんが、元々の目的が熱の発散を促して、熱暴走を防ぐ点にあることを考えれば、利用しない手はないでしょう。
最近のラズパイはCPU速度もあがり、特に発熱が問題になってきています。IoTプロジェクトをはじめる際にはヒートシンクを装着して開発を行ってください。
]]>